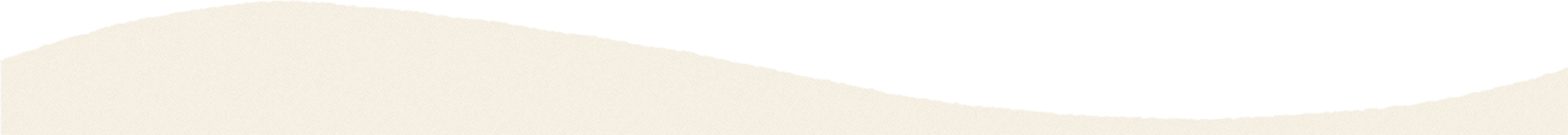
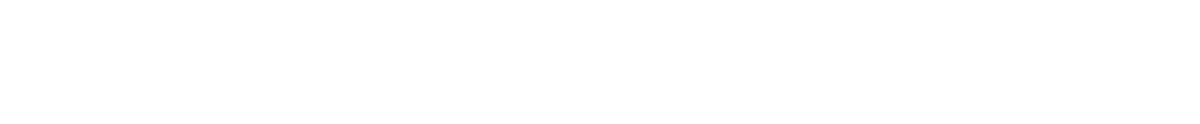
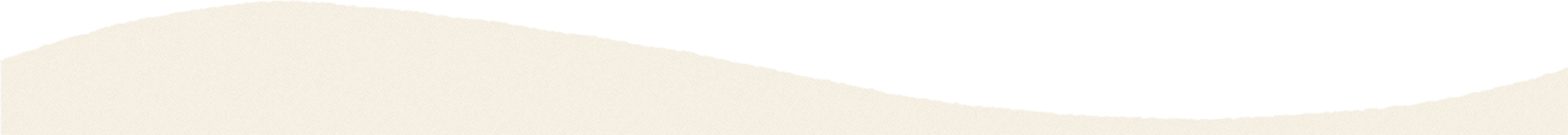
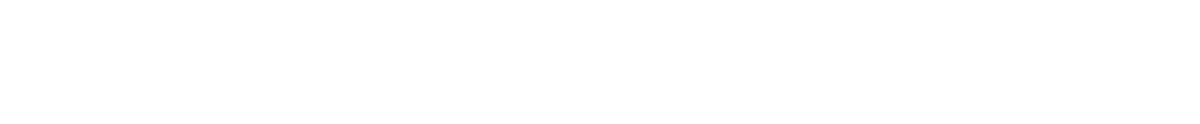
集落とまつりのなかにある食文化07
熊本県南部に残る、祭りや暮らしに根付いたマニアックで
ユニークな「食」を紹介するこのコーナー。
さて、最後に更新してから随分と時が流れてしまいました。お久しぶりの今回話題は、私の住む水俣でこの時期によく目にする、アレです!(今回は、マニアックではなくとってもメジャーかもしれません)
12月に入ると、水俣のいたるところで見かけるこんな風景。
 で、でっかい大根が
で、でっかい大根が
 こんなにたくさん
こんなにたくさん
 近寄るとこんな迫力が!!
近寄るとこんな迫力が!!
 なんだか、芸術的な作品にも見えてくるから不思議です。
なんだか、芸術的な作品にも見えてくるから不思議です。
さて、これ実は水俣や芦北地方では郷土の漬物として長年愛されている『寒漬(かんづけ)』と呼ばれる漬物用の大根を干しているところなのです。
一番寒くて、乾燥する時期に大根を寒風にさらして干し、いくつかの工程を経て漬物へと変身します。今回は少し簡単にですが、その様子をご紹介します。
 まず、収穫した大根をそのまま2週間ほど干します。
まず、収穫した大根をそのまま2週間ほど干します。
そして、塩漬けにしてまた2週間以上寝かせ…。


これが塩漬けして2週間ほど経った大根です。
私が住む水俣の越小場地域の食の名人、本井さんによると
両手で曲げた時に「つ」の字になるまで漬けておくのだとか。
 さあ、ここまできたらあと一息!
さあ、ここまできたらあと一息!
再度寒空の下に吊るして、からっからになるまで乾燥させます。
 私はこの寒漬用の大根が干してある風景が大好きで、今年は水俣のいろんな地域をうろつき、見かけたら畑にお邪魔して見学させていただきました。水俣のじいちゃんばあちゃんたちに、変なヤツだと思われたかもしれません…。笑
私はこの寒漬用の大根が干してある風景が大好きで、今年は水俣のいろんな地域をうろつき、見かけたら畑にお邪魔して見学させていただきました。水俣のじいちゃんばあちゃんたちに、変なヤツだと思われたかもしれません…。笑
 この御宅なんて、たくさんの経験を積みあと一歩で完成しそうなゴール間近の大根たちと、これから同じ道を歩む、まだこれから自分の身に何が起こるか分かっていない収穫されたばかりのみずみずしい大根たちのコラボレーションが…!なんとも言えません…!
この御宅なんて、たくさんの経験を積みあと一歩で完成しそうなゴール間近の大根たちと、これから同じ道を歩む、まだこれから自分の身に何が起こるか分かっていない収穫されたばかりのみずみずしい大根たちのコラボレーションが…!なんとも言えません…!
さあ、長い時間をかけて完成した寒漬用の干し大根がこちら。

これを新聞紙にくるんで、長期保存することもできるそうです。

これは2年もの。私が去年、近所の方にいただいたものです。
さて肝心の食べ方ですが、この干し大根をたっぷりの水で戻し、塩抜きをします。
そしてうすーくスライスして、醤油・うす口醤油・みりん・砂糖・酢などの調味料を合わせて煮立たせ、味付けします。これでやっと、『寒漬』として食べることができるのです。
そして寒漬はなんといっても、各家庭によって使用する調味料の配合や、そもそもの干し大根の塩抜き加減、塩抜き後にスライスするときの厚みなどバラバラ。
その家庭ごとにいろんな味の『寒漬』があります。

私はちょっと厚めに切って、コリコリとした食感を楽しむのが好きです。
味付けは、集落の食の名人の母ちゃんたちに教えてもらった秘伝レシピです!
お好みでショウガや昆布をいれてもバッチリ!白いご飯が無限にすすみます…笑
今回、数名のお母さんたちにお話しを伺いましたが、年々つくる人も少なくなってきたとのこと。

だけど、いつも卸している直売所のお客さんから「寒漬大根はまだ?」「今年はいつ頃出る?」と尋ねられたりして、『楽しみにしている人がいるからやっぱり今年もつくるのよ!』と仰っていました。
遠くに住むお子さんやお孫さんたちも楽しみにしていて、できたらたくさん送ったりするそうです。
私も初めて見た時は、「なんだこの黒い、醤油味が濃そうな漬物は!?」とびっくりしたのですが、実際食べてみて、つくってみてなんのなんの。南九州特有のあま~い甘い味付けで、たくさんの丁寧な工程を経て完成する『寒漬』のすっかり虜となってしまいました。
一番寒い季節に完成するのですが、食べるとなぜかあたたかさを感じる、地域の自慢の味なのです。

2019年3月まで八代市坂本町(旧坂本村)に住んでいましたが、現在は水俣市の旧久木野村へ。
ふるさと坂本をこよなく愛し、ケーブルテレビの仕事を通じて知り合った地域のじいちゃんばあちゃんの家に勝手にあがって縁側でお茶をすることが一番幸せを感じるとき。
自称、「集落の奇祭研究家」。明日はあなたのムラのマニアックなお祭りにお邪魔しているかも。現在は、主人が発行している『水俣食べる通信』の広報部長も務めています。